ワインは天候と非常に密接な関係に有ります。
ワイン造りは天候の占める割合が80%、残りの20%が醸造に関するプロの仕事と言われています。このように、ワイン造りにおいては「気温」「日照量」「風」の気象条件、「気候」「天候」「天気」がブドウ栽培に大きな影響を与えます。
農産物であるぶどうの味わいにはその年の天候が反映され、ワインの味わいにも、その年の天候の影響が刻まれます。同じ銘柄のワインでも、暖かかった年のワインは、果実味が豊かでまろやかに、反対に涼しかった年のワインは、酸がしっかりしてボリューム感よりもエレガントさが表現されるといったように、ぶどうが収穫された年の天候によって味わいに違いが出ます。
気候(⼀カ⽉以上の⻑期にわたる気象の平均的な状態)
気候と味わいの面では、緯度が高く寒い国と、緯度が低く暖かい国とを比較すると、やはり暖かい国の方がぶどうがよく熟します。ぶどうは熟すにつれて糖分が増し、酸度が低くなっていきます。そしてそれが、そのぶどうの特性を表現した味わいのワインになります。
例を挙げると、世界で最も緯度の高いワイン生産国の一つであるドイツのワインは酸が強くて軽やかな味わい。(ドイツのワイン法Qmpで補糖が許されています)逆に太陽が燦々と降り注ぐ南欧スペインのワインはアルコール度数が高くてリッチな味わいと言った感じです。
ただし、ワインの酸味やアルコール度数は、ぶどう品種の個性やぶどうの収穫時期などの影響も有ります。なので、一概に寒い国のワインが酸っぱくて軽やかな味わいで、温かい国のワインがアルコール度数が高くて丸い味わいだとは言い切れません。
葡萄の生育と四季の気候
当たり年にも悪いワインが出来る、不作の年でも良いワインが出来る、これは半ば真実ですが、総合的に分析すると、良いワインは良い葡萄から造られ、良い葡萄は好条件の天候のもとで育つ、という結論に落着きます。
晩秋と初冬
収穫が終わると、長い枝は剪定され、冬の寒さと霜に備えて畔の間の土を掘り返し株の根元に土をかけます。剪定は12月の中頃から始められます。葡萄のためには冬は寒いのが理想的です。
新年と春
剪定は、3月初旬ころまで続けられ株の根元の盛土は取り崩されます。
この時期は霜害が起こる可能性があり霜害が厳しく果実数が減少したとしても、その夏が非常に暑く乾燥していると、非常に濃度の凝縮した上質の葡萄が実ります。
晩春から初夏
霜の被害を受けていない場合は、畑の雑草が除去されウドンコ病やベト病予防策が取られ、
葡萄の開花を待ちます。暖かく乾燥しているのが理想的で、そうなれば開花は早く短期間で終わります。
開花が早ければ早いほど収穫期も早まり収穫のリスクから逃れられます。古来から、開花から摘み取りまで100日が必要とされています。
盛夏から晩夏
穏やかな太陽の光は葡萄の実が熟すのを助け、少量の雨は実を大きくしてくれます。8月は比較的無事に過ぎることが多い季節で葡萄の実の色はどんどん変わっていきます。
豊作の気配が感じられる年には、高級葡萄園では、葡萄の房を思いきって切り減らします。
初秋
晩夏と初秋の熟成の時期は、葡萄の実の糖分含有量とその他の成分のバランスが決まる段階と言えます。 酸味と糖分のバランスは非常に重要で、葡萄が良く熟せば、それだけ糖分の含有量が高くなり、発酵後のアルコールの濃度も高くなります。但し熟し過ぎると酸分は減少するというコントロールの難しい部分でもあります。
酸味はワインの生命であり、活力源であり、新鮮さを保ち、寿命を支える力をもたらします。
収穫は、葡萄が適度に熟した寒くなる前に行なわれます。ボルドー地方で言えば、9月半ばでは早すぎます。通常9月末が望ましく10月末になるとリスクが多くなります。
天候(⼀週間や⼀カ⽉など⽐較的短い期間の気象状態)
雨が少ない・湿気が少ないことがブドウにとっては良いといえます。暑すぎず雨が降りすぎずが一番です。湿気が多いとベト病になりブドウが全滅する恐れがあり、暑すぎると害虫が大量発生する可能性が高く、葉を全部食べつくします。
収穫前の天候は非常に大切で、天気がよければ糖分が上がり、雨が降ると当分が薄まります。
ワインにおいてのヴィンテージとは、ぶどうの収穫から醸造を経て瓶詰めされるまでの工程を表す言葉ですが、晴れが多くてぶどうがよく熟した年のワインの事をヴィンテージワイン、ぶどうの収穫年のことをヴィンテージともいいます。
ちなみに、低価格の量販ブランドワインなどでは、色々なぶどうをブレンドする事でブランドの味わいを表現しているので、ヴィンテージの個性は現れにくくなっています。


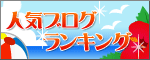








0 件のコメント:
コメントを投稿